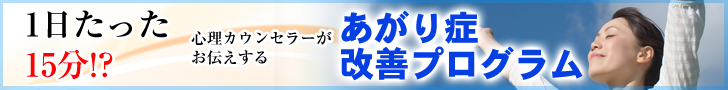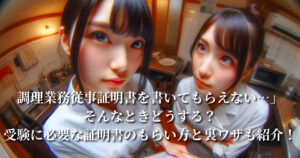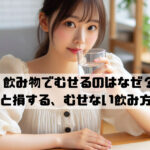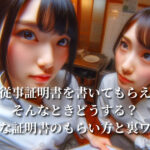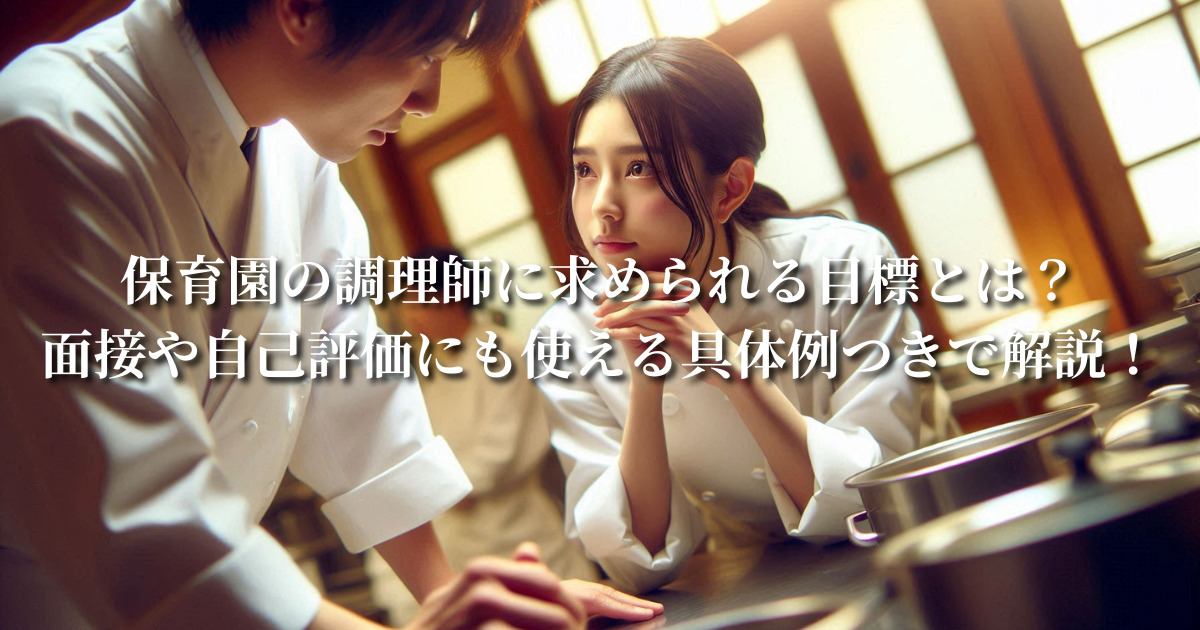
「目標を書いてください」——保育園の調理師として働いていると、面接や年度初めの自己評価のときによく言われますよね。
でも正直なところ「そんなの現場の忙しさを知らない人のセリフじゃない?」って思ったことありませんか?
朝から食材の下処理に追われて給食を作って配膳して片付けた後に午後のおやつ。
目まぐるしく過ぎる毎日で「自分の目標って…なんだっけ?」と手が止まってしまう人も多いと思います。
そこで今回は、保育園の現場で実際に働く調理師目線で「目標設定」のヒントをお届け!
面接や書類用のフォーマルなものから自己評価で使える実用的なものまで、そのまま使える具体例付きで紹介していきます。
肩ひじ張らずに、コーヒー片手に気楽に読んでいってくださいね。
調理師の「目標設定」で悩む人が増えてます

なぜ保育園の調理師に「目標」が求められるのか?
その背景と実際の現場とのギャップについてお話しします。
「目標っているの?」
「結局ただの形式じゃない?」
そんなモヤモヤに、現場目線で向き合っていきます。
現場はてんてこまい。でも「目標」は求められる
保育園の調理師に「目標」を求められる機会って実は年々増えてるんです。
たとえば…
- 面接のときに「今後の目標はありますか?」と聞かれる
- 年度初めの自己評価シートで「1年の目標」を書く欄がある
- 年度末に「目標達成できたか」を振り返る場面がある
こういうの、ありますよね。
私も正直、最初は「料理を出すだけで精一杯なのに何を書けばいいの!?」と思ってました。
でも、どうやらこれには「園の方針」や「人材育成の一環」という、上の人たちの考えがあるんです。
つまり「この人がどんな想いで、どんな風に働こうとしてるのか」を言葉で見たいんですね。
でも正直…そんな余裕ないよね?
現場にいると、こう思いませんか?
- 給食の量が多すぎて毎日バタバタ
- 子どもたちのアレルギー対応で神経ピリピリ
- 調理以外にも掃除、片付け、衛生管理…
目標なんて立てる前に、毎日を無事に終わらせるので精一杯。
「安全に食事を出せただけで花丸でしょ!」って気持ち、すごくよくわかります。
でも実は、そういう「現場ならではのリアルな感覚」こそが目標に活かせるポイントになるんです。
このあと紹介していくコツを使えば「ただの建前」じゃない本当に意味のある目標が作れますよ!
よくある「ダメな目標」とは?

多くの保育園調理師がつまずきやすい「ありがちな失敗例」を紹介。
なんとなく「よさげ」に見えるけど、実は意味が伝わっていない「ダメな目標」を分析していきます。
なぜそれがNGなのか、上司や人事の視点からもわかりやすく解説します!
「いいこと言ってるのに通らない」のはナゼ?
調理師の目標って、いざ書こうとするとついこうなりがちです。
- 子どもたちに喜んでもらえるような給食を作りたい
- 安全第一で調理に取り組みたい
- 子どもたちが笑顔になるようにがんばる
うん、言いたいことはすごくよくわかります。
でも、これらの目標は「気持ちは伝わるけど評価にはつながらない」パターンです。
よくあるダメ目標の特徴3つ
よくある駄目なパターンの目標が、実はとっても多いんです。
| ダメ目標の特徴 | 内容例 | なぜダメか? |
|---|---|---|
| 抽象的すぎる | 「子どもたちに喜んでもらう給食を作る」 | 何をどうするのかが不明。具体的な行動が見えないので、評価や改善ができない。 |
| 誰でも言える | 「安全第一を心がける」 | 全員に共通する“前提条件”なので、あえて目標に書くと弱く見える。 |
| 書いて満足して終わる | 「〇〇に取り組みたい」で終わる | 実行や振り返りがなく、行動と結果がセットになっていない。 |
「なぜ伝わらないのか?」を人事・上司の視点で考える
たとえば、あなたが上司だったとします。
部下が「安全に給食を出したい」と言ったら、どう思いますか?
「それって、あたり前じゃない?」って思いませんか?
評価する側の人たちは、「どんな行動をする人なのか」を見たいんです。
なので、あいまいな表現や一般論では伝わらないんですね。
逆に言えば、「この人は現場のどこに課題を感じて、どう動こうとしてるのか」が見える目標ならグッと信頼感が増します。
ありがちだけど危険な「自己満足型目標」
そしてもう一つ落とし穴なのが「書いたら終わり」になってしまう目標。
- 形だけ目標を立てる
- でも現場では実行できていない
- そのまま1年が過ぎていく…
これだと、目標自体がただの形式的な作業になります。
そうならないためには、「数字」「行動」「期間」が含まれていることが大切です(次の章でくわしく解説します!)
目標は「やってること」を言葉にすること
理想や想いを書くのも大切だけど、それだけじゃ相手には伝わりません。
目標とは「やってること」や「やろうとしてること」を、誰が見ても分かる形に言葉で表すことなんです。
次は、じゃあ、どうすれば現場のリアルが伝わる目標になるのか?を、しっかり掘り下げていきます!
目標はこう考える!調理師ならではの「現場視点」が武器

調理師の仕事って、ただ料理を作るだけじゃない。
「食育」「アレルギー対応」「子どもの反応」など、保育園だからこそ向き合うことがたくさんあります。
現場でしか見えない「強み」を目標に活かすコツを紹介します。
調理師の目標は「現場力」で差がつく!
調理師の仕事は、調理室の中だけで完結しません。
むしろ、子どもたちの声や日々の給食の様子が一番のヒントになります。
- 「今日はよく食べてたな」
- 「あの子、にんじんだけ残してたな」
- 「食べるスピードが遅くなってるかも?」
こういう「現場の小さな変化」に気づけるのが保育園の調理師としての最大の強みです。
食育活動と連動した目標を立てよう
食育は保育園の中でも大事な柱です。
栄養士や保育士と連携して調理師が関われる場面も増えてきています。
たとえば、こんな目標が考えられます。
- 「野菜の皮むき体験を年に2回実施する」
- 「食材の話を給食だよりに毎月1品紹介する」
- 「おにぎりづくりイベントを年度内に1回開催する」
👉 ポイントは「調理師が関われる範囲で現実的にできること」に落とし込むこと。
ただ「食育を大事にしたい」ではなくどんなアクションを起こすかが目標になると一気に現実味が出ます。
アレルギー対応の工夫は「責任感」が伝わる目標に
アレルギー対応は、命に関わる大事な仕事。
でもそれって、ただ「ミスをしない」だけじゃないんです。
- 誤配を防ぐチェック体制の見直し
- 代替食材の研究や記録の継続
- アレルギー児の食事を“寂しく見せない”盛りつけ工夫
こういったことに目を向けると「責任感のある人」として評価されます。
アレルギー対応の目標例
- 「アレルギー児への配膳ミスをゼロに保ち、チェック体制を見直す機会を年3回設ける」
- 「代替献立の写真と記録を月1回ファイリングして、職員間で共有する」
ただ「安全に配慮します」ではなく「どうやって?何を?どのくらいの頻度で?」まで書くのがコツ。
子どもや保護者の声を「ヒント」に
調理師の仕事って、意外とフィードバックをもらいにくいもの。
でも保育士さん経由や保護者アンケート、行事のときの感想などに注目すると宝の山です。
- 「〇〇が大好きみたいで、家でも作ってって言われました!」
- 「季節感のあるメニューがうれしかったです」
- 「今日は完食でした!」
これらの声から、目標を逆算することもできます。
たとえば…
- 「園児の「好き」を取り入れたメニューを季節ごとに1回以上導入する」
- 「行事食のテーマ性を深めて、保護者からの感想を記録として残す」
👉 子どもたちや保護者の声って、ただの「感想”」じゃない。
調理師が前向きに活かせる「改善のタネ」なんです。
机の上じゃなく「現場に目標のヒント」がある!
調理師ならではの目標は、「現場の空気」と「目の前の反応」からしか生まれません。
数字を追う前に、いつもの景色をちょっと深く見てみると自分らしい目標が見えてくるはずです。
そのまま使える!目的別 目標例テンプレ集〜コピペして使える保存版〜

自己評価・目標管理シート用(現職向け)
園内での業務目標として提出する場合は、「具体性・回数・改善意識」がキモ。
上司が読んでも「考えてるな」と伝わる例を集めました。
✅ 食べやすさ・好き嫌い対応
- 「好き嫌いの多い子にも楽しく食べてもらえる工夫を年間で5回以上実施する」
- 「野菜が苦手な園児にも“食べてみよう”と思わせる献立や盛り付けを月1回意識する」
- 「残菜の多い献立を記録し、月ごとに改善案を1つ提案する」
✅ アレルギー・安全管理
- 「アレルギー児への提供ミスゼロを継続し、毎月1回チェック体制を見直す」
- 「アレルギー対応食の盛り付け写真を記録に残し、職員と共有する機会を年3回設ける」
- 「代替食材の知識を深めるため、年2回以上、外部資料や研修を活用する」
✅ 食育・園との連携
- 「保育士と連携して、季節の食材に関する食育掲示を年4回作成する」
- 「調理師として食育活動に年に1回以上参加し、子どもと関われる場を広げる」
- 「行事食や特別メニューについての説明を毎月1回“給食だより”に掲載する」
✅ 子ども・保護者の声の活用
- 「保護者アンケートの“食事に関する声”をもとに、献立改善を年2回行う」
- 「保育士からのフィードバックを活かし、人気メニューの再登場率を意識する」
- 「園児の反応を記録し、月1回職員会議で共有する」
転職・就職用(面接・履歴書用)
こちらは「志望動機」や「自己PR」に使えるよう、少し理想を盛りつつもリアリティを忘れず構成。
「私はこういう姿勢で仕事しています」が伝わる言葉を意識しています。
✅ 食育・献立への思い
- 「保育園の食事を通じて、五感を育てるメニューを月1回提案したい」
- 「栄養だけでなく“季節感”や“文化”を伝えるような献立づくりを大切にしている」
- 「子どもたちが“また食べたい”と思えるような献立作成を目指している」
✅ 調理師としての姿勢・目標
- 「ただの“給食”ではなく、“記憶に残る食体験”を提供することを目標にしている」
- 「安全・衛生を最優先にしながらも、子どもたちの“楽しい気持ち”を大切にしています」
- 「アレルギー対応に責任を持ち、安心して任せてもらえる存在を目指しています」
✅ 園との連携・チーム意識
- 「保育士や栄養士と連携し、現場の声を取り入れた給食づくりに努めたい」
- 「調理室にこもるのではなく、“園全体の一員”として関わる意識を持っています」
- 「行事や季節に合わせた“特別メニュー”を通じて、子どもの思い出に残る給食を目指しています」
✅ 自分の成長につなげる姿勢
- 「子どもの変化に気づける“観察力”を活かし、食べ残しや食べにくさの改善につなげたい」
- 「現場での経験を記録し、次年度以降の給食運営に活かしていくことを目標にしています」
【目標テンプレ活用のコツ】
- 数字や頻度を入れると、目標としての「実行力」がUP
- 漠然とせず、「誰に・何を・どうしたいか」がハッキリしてると評価されやすい
- 特に自己評価では「工夫」や「改善」が伝わるかがカギ!
目標づくりは「自分の価値を言語化する」こと

「目標を書くのが苦手」っていう調理師さん、多いです。
でもそれって、スキルや意欲がないんじゃなくて——
「日々の頑張りが当たり前すぎて、わざわざ言語化したことがない」だけなんです。
■ 自分の仕事を「翻訳」するだけで伝わり方は変わる
たとえば…
- 「いつも確認してる」→「アレルギー対応の確認を、ダブルチェック体制にしてミスゼロを目指す」
- 「工夫して盛り付けてる」→「食べ残しが多いメニューは盛り付けの工夫で改善し、月ごとに評価する」
こんなふうに書くだけで、「見てないところでしっかり考えてるんだな」って相手に伝わります。
それこそが「自己評価」や「履歴書」で一番大事な部分。
■ 調理師の現場目線は、現場にいる人にしか書けない
たとえば園児の反応や、保育士とのちょっとした会話、行事メニューの一工夫。
そういう「現場のリアル」を言葉にできるのは、書類だけを見てる人にはできないんです。
だからこそ「書ける=武器になる」。
あなたが日々やっていることは、ちゃんと価値がある。
あとはその価値を、「相手に届く形」に整えるだけなんです。
■ 目標は「評価されるため」だけじゃない
実は一番のメリットは——
自分のやっていることを自分で認められるようになること。
なんとなく働いてるように感じてた日々も、「こんな工夫した」「あの反応がうれしかった」って記録していけば、ちゃんと意味のある仕事だったって思えるようになる。
それは転職活動の武器にもなるし、今の職場での自信にもなる。
最後に一言
目標を書くことは、自分の努力にスポットライトを当てること。
やってることが地味でも、それを「言語化できる人」が、最後に評価される。