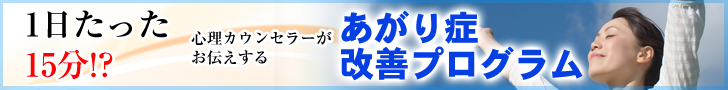保育園で働く調理師にとって、自己評価を書く機会は少なくありません。
年度末の人事評価や昇給のタイミングで「どんなことを書けばいいの?」「評価が上がる書き方は?」と悩むこともあるでしょう。
特に、日々の業務が忙しく「頑張ったけれど、具体的にどう伝えればいいのかわからない」という声も多いです。
そこで今回は、自己評価の目的や書き方のコツと例文まで加えて詳しくお伝えします。
自己評価を上手に書いて、あなたの努力をしっかりアピールしましょう!
保育園調理師の自己評価とは?

自己評価の目的とは?
保育園の調理師が自己評価を書く理由は、大きく3つあります。
- 人事評価に活用される
→ 園の管理者や本部が、日々の働きぶりを評価する材料になります。 - 昇給や賞与に影響する
→ 良い評価が得られれば、昇給や賞与の額が変わることも。 - 自分のスキル向上につながる
→ 自分の強みや改善点を振り返ることで、より良い調理ができるようになります。
「単なる作業報告ではなく自分の成長をアピールするために書くもの」と考えると、モチベーションも上がりますね。
どんな視点で評価されるのか?
保育園の調理師の自己評価では、主に次のような点がチェックされます。
| 評価項目 | チェックされるポイント |
|---|---|
| 調理技術 | 食材の扱い方、調理スピード、献立の工夫 |
| 衛生管理 | 食品の適切な保存、調理器具の消毒、食中毒対策 |
| コミュニケーション | 園児・保護者・職員とのやりとり、チームワーク |
例えば、調理のスピードが上がったり、子どもたちが喜ぶ工夫をしたり、衛生管理の取り組みを強化したりすることが評価されます。
また、調理だけでなく「他の職員や保護者との関係を良好に保てているか」も重要です。
食事は保育の一部なので、他の先生と連携しながら改善に取り組む姿勢が求められます。
自己評価の書き方のポイント

自己評価を書くときに大切なのは、「ただ業務をこなした事実を書く」のではなく、「自分がどのように成長し、どんな成果を出したか」を伝えることです。
評価する側は、あなたの頑張りを直接見ているわけではないので伝え方次第で印象が大きく変わります。
評価を上げるための3つのポイントを解説します。
ポジティブに書く(課題よりも成長・努力を強調)
自己評価では、ネガティブな表現を避け、前向きな成長や努力をアピールすることが重要です。
「できなかったこと」よりも「どのように改善したか」を伝えましょう。
✅ NGな書き方
❌ 「忙しくて時間が足りず効率的に作業できなかった」
❌ 「衛生管理は意識していたが忙しさで徹底できなかった」
このような書き方だと「この人はまだ問題を解決できていない」と判断されてしまいます。
✅ OKな書き方
⭕ 「忙しい時間帯でもスムーズに作業できるように、食材の仕込み時間を見直し効率的な調理を意識した」
⭕ 「衛生管理の徹底を意識し、作業後の消毒リストを作成。結果として、衛生チェックの基準をクリアし続けることができた」
→ ポイントは「改善点をポジティブに変換する」こと!
具体的なエピソードを入れる(「○○の改善に取り組んだ結果、○○が向上した」)
評価を上げる自己評価を書くには「何をどう改善し、どんな成果があったか」を明確にすることが大切です。
✅ 具体例1(調理の効率化)
「提供時間を短縮するために野菜のカット方法を見直した。その結果、調理時間が1日あたり20分短縮でき園児が温かい食事を食べられるようになった。」
✅ 具体例2(アレルギー対応の改善)
「アレルギー児のためのメニューを見直し、保護者と相談しながら安心して食べられるレシピを考案した。その結果、保護者からの信頼が高まりアレルギー対応の問い合わせが減少した。」
「やりました!」だけではなく「その結果どうなったか」を必ずセットで書くのがポイント!
客観的な視点を加える(「園児の食事残しが減少」などのデータ活用)
自己評価は主観的になりがちですが、数字や具体的な成果を入れると説得力が増します。
✅ 客観的なデータを入れる例
- 「新しい献立を導入し、園児の食べ残しが 30%減少 した」
- 「調理手順を見直したことで、作業時間が 1日15分短縮 できた」
- 「保護者アンケートの食事満足度が 85%→92% に向上 した」
→ データがあると、評価する側も納得しやすい!
自己評価でよくあるミスと改善策

自己評価を書くとき、意外とやってしまいがちなミスがあります。
適当に書くと「何をアピールしたいのかわからない」「評価につながらない」となってしまうことも…。
よくあるミスとその改善策を具体的に解説します!
「頑張りました」だけでは伝わらない → 数値や具体例を入れる
ミスの例
「毎日、調理を頑張りました。忙しい日もありましたが、しっかりやり切りました。」
→ これでは、どんな努力をしたのか、何が改善されたのかが伝わりません。「頑張った」だけでは評価されにくいのが現実です。
改善策
「どんな工夫をしたか」「その結果どうなったか」を具体的に書くこと!
特に「時間」「回数」「数値」などのデータを入れると、より説得力が増します。
✅ 改善後の例文
「調理の効率化を意識し、作業工程を見直しました。その結果、仕込み時間を1日30分短縮でき、子どもたちに温かい食事を提供できるようになりました。」
→ 数値を入れるだけで、どれだけ改善したのかが明確に!
ネガティブな内容を避ける → 課題も前向きな表現にする
ミスの例
「忙しすぎて調理が間に合わない日がありました。人手が足りず、大変でした。」
→ これでは「できなかったこと」ばかりが目立ち、評価を下げる可能性も…。
ネガティブな内容を書くときは、必ず前向きな改善策をセットにする のがポイント!
改善策
✅ 改善後の例文
「忙しい時間帯の調理をよりスムーズに進めるため、作業の優先順位を整理しました。その結果、混雑しやすい時間帯の負担を軽減し、調理ミスの削減につながりました。」
→ 課題を書きつつも、「どう改善したのか」「成果が出たのか」までセットにすると評価されやすい!
(3) 型にはめすぎると個性が出ない → 自分の工夫を入れる
ミスの例
「衛生管理を徹底しました。手洗いをしっかり行い、調理器具の消毒をしました。」
→ これでは当たり前の内容すぎて、特に評価につながりません。他の調理師と差別化するには、「自分がどんな工夫をしたか」を書くのが大事!
改善策
✅ 改善後の例文
「衛生管理の意識向上のために、調理チーム内でチェックリストを作成し、日々の確認を徹底しました。また、園児にも衛生意識を持ってもらうため、食事前の手洗いを楽しく学べるポスターを作成し、園内に掲示しました。」
→ 自分ならではの取り組みや工夫を入れると、一気に評価ポイントがアップ!
保育園調理師の自己評価の例文

自己評価を書くときは、単なる作業報告ではなく、「自分がどのように工夫し、その結果どうなったのか」を伝えることが大切です。
評価を上げるための自己評価の例文を3つのポイントに分けて紹介します。
ですが、先ほどもお伝えした通り、自分ならではの取り組みや工夫を追加することを前提にしてくださいね。
例文については「保育園調理師の自己評価の例文続き」も参考にしてください。
調理スキルの向上をアピールする例文
ポイント
- 「効率的な作業」「調理時間の短縮」「食事の質向上」を強調する
- 具体的な改善策と成果をセットで書く
例文
「日々の調理業務において、より効率的な作業を意識し、調理時間の短縮を実現しました。例えば、野菜の下処理方法を見直し、包丁作業をカット済み食材と組み合わせることで、仕込み時間を1日あたり30分短縮しました。その結果、提供時間に余裕が生まれ、子どもたちが温かい状態で食事を楽しめるようになりました。
また、作業工程を整理し、調理チーム内で役割分担を最適化したことで混雑しやすい時間帯の負担を軽減。結果として提供の遅れがなくなり、先生方からもスムーズになったと評価をいただきました。」
→ 「時間短縮」+「食事の質向上」+「チームワーク向上」まで盛り込むのがポイント!
衛生管理の取り組みをアピールする例文
ポイント
- 「衛生管理の徹底」「数値データ」「改善策」をセットで書く
- 結果として「安全性が向上したこと」を強調
例文
「衛生管理の徹底に努め、調理器具の消毒手順を改善しました。これまでは調理後の消毒が個々の判断に任されていましたが、消毒チェックリストを導入しスタッフ全員が統一された方法で作業できるようにしました。
その結果、細菌検査の数値が前年と比べて25%減少し、安全な食環境の維持に貢献できました。また、手洗いの徹底を促すためにポスターを設置し、子どもたちにも衛生管理の意識を持たせる取り組みを実施。これにより、先生方からも『子どもたちが積極的に手を洗うようになった』と好評をいただきました。」
→ 「具体的な改善策」+「データ」+「先生や子どもへの影響」まで入れると説得力UP!
(3) 園児や保護者とのコミュニケーションをアピールする例文
ポイント
- 「保護者の信頼獲得」「子どもたちの食事環境改善」「アンケートなどの数値」を入れる
- 相談や要望にどのように対応したかを具体的に書く
例文
「保護者からの食事に関する相談に積極的に対応し、アレルギー対応メニューの改善に努めました。アレルギー児の保護者との個別面談を定期的に実施し、事前に不安点を確認する仕組みを作りました。その結果、『給食が安心して食べられるようになった』という声を多くいただき、保護者アンケートの食事満足度が85%から92%に向上しました。
また、園だよりに『給食室だより』のコーナーを設け食材のこだわりやレシピを紹介することで、保護者からの関心が高まりました。これにより、食事に対する質問が増え、給食への理解が深まるきっかけにもなりました。」
→ 「保護者対応の工夫」+「数値データ」+「園全体の意識向上」までしっかり盛り込む!
まとめ:自己評価をする事で成長に繋げていこう

保育園の調理師として、自己評価を書くのは決して簡単なことではありません。
でも、評価を上げるためにも自分の成長を振り返るためにも、しっかりと書くことが大切です!
自己評価は“成長の証”
「自己評価を書くのが苦手…」という人も多いですが、
✅ 自分が努力したことを振り返る
✅ 仕事の成果を整理する
✅ さらに成長するためのヒントを得る
という意味でも、とても大切な作業です!
💡 最後のワンポイントアドバイス!
📌 「誰かに話すつもりで書くとスムーズに書ける!」
📌 「ポジティブ&具体的に書くと評価されやすい!」
今回の内容を参考に、自分の頑張りをしっかり伝えられる自己評価を書いてみてくださいね!